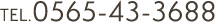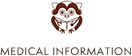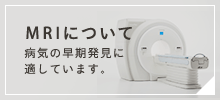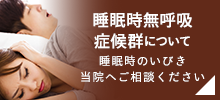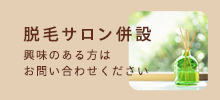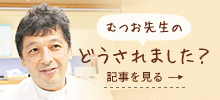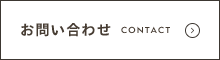本日は、漢方の勉強会に出席してきました。
頭痛治療を中心のお話で、大変勉強になりました。
私は、開業するまでは脳神経外科医師として勤務してきました。
とかく、脳神経外科医の間では、手術の技術や、高度な検査について話し合われることが多かったので、私にとって漢方はとっつきにくく、ほとんど勉強したことがありませんでした。
恥ずかしながら、慢性硬膜下血腫の改善効果があるとされる五苓散というお薬以外は、ほとんど処方したことがなかったのです。
しかし出席してみたら、講師の先生はなんと脳神経外科医の先生でした!
なぜこの先生は脳神経外科医なのに、まるで内科医のように東洋医学に携わっているんだろうか、不思議に思いました。
しかし話をきいて、なるほど、と納得しました。
頭痛やめまいに効く漢方がこんなにもたくさん種類があり、それぞれどんな症状の頭痛に効くのか、その根拠としての成分はなにか、わかりやすく説明してくださり、何だか目からウロコが落ちた気がしました。
西洋医学では、とかく診断が検査に頼ってしまうのに対し、東洋医学では触診や視診など患者さんに直接接して診察(四診)することが基本です。
診察した結果で、診断(証)をくだし、その患者さんの症状にあった薬を処方(方剤投与)、という手順です。
診察が基本ですから、東洋医学を実践すれば、患者さんとのコミュニケーションがよくとれて信頼関係が生まれる、とのこと、本当に同感でした。
これからは私も漢方をもっと勉強し、患者さんの治療に生かしていきたいと思います。
そのきっかけを作ってくださった、この勉強会と講師の先生、ありがとうございました。
カレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最新記事
アーカイブ
- 2025年3月 (2)
- 2025年1月 (2)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (2)
- 2024年9月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年5月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (2)
- 2024年2月 (1)
- 2024年1月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年11月 (2)
- 2023年10月 (2)
- 2023年8月 (1)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (1)
- 2023年4月 (2)
- 2023年3月 (2)
- 2023年2月 (2)
- 2023年1月 (2)
- 2022年10月 (2)
- 2022年9月 (1)
- 2022年7月 (2)
- 2022年3月 (2)
- 2022年1月 (2)
- 2021年12月 (1)
- 2021年11月 (1)
- 2021年10月 (1)
- 2021年9月 (1)
- 2021年8月 (1)
- 2021年7月 (1)
- 2021年6月 (1)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (2)
- 2021年3月 (1)
- 2021年2月 (1)
- 2021年1月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年11月 (2)
- 2020年10月 (1)
- 2020年9月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年7月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2020年5月 (3)
- 2020年4月 (2)
- 2020年3月 (2)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (2)
- 2019年9月 (1)
- 2019年8月 (1)
- 2019年1月 (1)
- 2018年12月 (1)
- 2018年11月 (1)
- 2018年10月 (1)
- 2018年9月 (2)
- 2018年6月 (1)
- 2018年5月 (1)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年1月 (1)
- 2017年11月 (3)
- 2017年10月 (6)
- 2017年9月 (2)
- 2017年8月 (2)
- 2017年7月 (1)
- 2017年6月 (3)
- 2017年5月 (2)
- 2017年4月 (5)
- 2017年3月 (4)
- 2017年2月 (2)
- 2017年1月 (3)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (4)
- 2016年10月 (3)
- 2016年9月 (4)
- 2016年8月 (3)
- 2016年7月 (2)
- 2016年6月 (3)
- 2016年5月 (4)
- 2016年4月 (6)
- 2016年3月 (6)
- 2016年2月 (5)
- 2016年1月 (4)
- 2015年12月 (4)
- 2015年11月 (5)
- 2015年10月 (3)
- 2015年9月 (2)
- 2015年8月 (3)
- 2015年7月 (3)
- 2015年6月 (4)
- 2015年5月 (4)
- 2015年4月 (5)
- 2015年3月 (3)
- 2015年2月 (4)
- 2015年1月 (4)
- 2014年12月 (4)
- 2014年11月 (9)
- 2014年10月 (1)